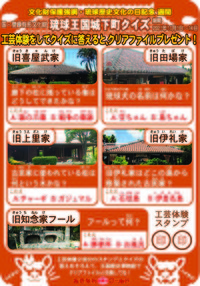2017年06月08日
沖縄の稲作と「五月ウマチー」
はいたい!
王国歴史博物館です <今回は伝統行事の紹介です!
<今回は伝統行事の紹介です!
明日、6月9日(旧暦5月15日)は「五月ウマチー」
神様に稲の初穂を供えて、豊作を祈願する伝統行事です。
地域によっては稲穂祭、シチュマ、シキョマ、スクマ、マイスクマなどとも呼ばれ、琉球王国時代には国を挙げて盛大におこなわれていました。
さて、沖縄の稲といえば。
実は当博物館にも、よくこんな質問が寄せられます。
「沖縄にはなぜ田んぼがないのか」
確かに、車で走っていても全くと言って良いほど、田んぼを見かけることはありません。
ですが違うんです。
沖縄にも田んぼはあります!

沖縄本島北部、名護市羽地の田んぼ
(※内閣府沖縄総合事務局農林水産部農村振興課提供)
沖縄県農林水産部農林水産総務課の統計にも、「平成26年は、作付面積860ha、収穫量2240トン」と表れています。
とはいえ統計のように、現在の生産量はあまり多くありません。
しかしこの「五月ウマチー」という行事を見てもわかるように、かつての沖縄では今よりも稲作が盛んにおこなわれていました。
稲作が減少したのには、いくつかの要因があります。
①昭和30年ごろ、世界的に砂糖が高騰し、多くの農家が稲作より換金性の高いさとうきび作へと切り替えた。
②戦後、他の都道府県から安価で美味しい米が入るようになった。
③そもそも、沖縄の土壌は水はけがよく、河川は少なく、かつ台風があるなど稲作が難しい土地柄だった。
以上のことから、現在では稲作よりもさとうきび、ゴーヤーなどの野菜類、果樹などの生産が増えています。
こういった生活環境の変化によって、かつては王国を挙げておこなった伝統行事「五月ウマチー」も、近年では簡素化され、若い世代では知らない人も多い行事となってしまいました。
王国歴史博物館です
 <今回は伝統行事の紹介です!
<今回は伝統行事の紹介です!明日、6月9日(旧暦5月15日)は「五月ウマチー」
神様に稲の初穂を供えて、豊作を祈願する伝統行事です。
地域によっては稲穂祭、シチュマ、シキョマ、スクマ、マイスクマなどとも呼ばれ、琉球王国時代には国を挙げて盛大におこなわれていました。
さて、沖縄の稲といえば。
実は当博物館にも、よくこんな質問が寄せられます。
「沖縄にはなぜ田んぼがないのか」
確かに、車で走っていても全くと言って良いほど、田んぼを見かけることはありません。
ですが違うんです。
沖縄にも田んぼはあります!

沖縄本島北部、名護市羽地の田んぼ
(※内閣府沖縄総合事務局農林水産部農村振興課提供)
沖縄県農林水産部農林水産総務課の統計にも、「平成26年は、作付面積860ha、収穫量2240トン」と表れています。
とはいえ統計のように、現在の生産量はあまり多くありません。
しかしこの「五月ウマチー」という行事を見てもわかるように、かつての沖縄では今よりも稲作が盛んにおこなわれていました。
稲作が減少したのには、いくつかの要因があります。
①昭和30年ごろ、世界的に砂糖が高騰し、多くの農家が稲作より換金性の高いさとうきび作へと切り替えた。
②戦後、他の都道府県から安価で美味しい米が入るようになった。
③そもそも、沖縄の土壌は水はけがよく、河川は少なく、かつ台風があるなど稲作が難しい土地柄だった。
以上のことから、現在では稲作よりもさとうきび、ゴーヤーなどの野菜類、果樹などの生産が増えています。
こういった生活環境の変化によって、かつては王国を挙げておこなった伝統行事「五月ウマチー」も、近年では簡素化され、若い世代では知らない人も多い行事となってしまいました。
Posted by おきなわワールド(工芸) at 14:29│Comments(0)